|
N氏、今度は、ドストエフ
スキーのもとへ行く (1)
[ by Seigo ]
名前:Seigo
投稿日時:
09/01/07(水)・15(木)・26(月)
更新:26/02/13
201×年×月、日本の大分県に住む40歳のN氏は、東西の過去のその秘技や人間の秘めた超能力の長年にわたる研究及び独自の修行により、心を集中して心の内でその時代・場所の詳細を唱えるだけで瞬時に過去現在未来を行き来できるタイムワープの秘術をひそかに得た。
N氏は、その後、あくまで友人や家族にも秘密裏(ひみつり)に、七ヶ月の間に、単身で過去未来への七回にわたるタイムワープの実行を重ねた。この実行により、彼が知りたかった、聖徳太子、空海、明智光秀、サン・ジェルマン伯爵、ヒットラーをめぐってのいくつかの事実と、22世紀の初めに日本に現れてこの私たちの地球世界を大きく変革し救済する超人グループQのことを知ることができた。その過程における様々な見聞、危険も伴った体験、秘儀や文物の入手によりN氏はいろんな面で所持や成長を得たと言えよう。
かなりのドストエフ好きーでもあった彼は、今度は、敬愛するドストエフスキーに会いドストエフスキーのことについていろいろと実地に知るべく、ドストエフスキーの事跡のことをより
詳しく復習し一週間でロシア語会話の基礎を速習し、ドストエフスキーのあの時あの場所にも行(い)ってみることにした。行ってみたいドストエフスキーのあの時あの場所はいくつもあるので、今回以降も、いくたびか別の時期場所のドストエフスキーのもとへ訪れることになるだろう。
出発。――― まもなくして、時期は西暦1879年5月某日[※注1]、場所はペテルブルクのヤムスカヤ通りに面するアパートの一部屋[※注2]の片隅に、N氏のその目と身体が現れた。その暗い部屋の机の上には二本の燭台に大きめの蝋燭(ろうそく)が灯(とも)されていて、その机の椅子に腰をすえて何ごとかに耽(ふけ)っている様子の頭 でっかちな男の後ろ姿が見える。その後ろには長いソファーがあり、同じく後ろの壁に掛けられているラファエロ作の絵「システィナのマドンナ」が蝋燭の光り
を受けてなんとか見分けられた。テーブルの上の置き時計[※注3]の針は深夜のちょうど12時半[※注4]を指し、部屋の中には煙草の臭(にお)いがかすかに漂っている。
「フョードル・ミハイロヴィチ殿(どの)!」
ペテルブルクのドストエフスキーの住まいの書斎の中を映した写真をすでに見ていたN氏は、あらかじめ決めていた通り、ほんの三メートル左斜め先にいるドストエフスキーに向けて、ささやき声で呼びかけた。その間、N氏の内に生(なま)ドストエフスキーに会えたという思いが熱く込み上げていたのは言うまでもない。明日にはアンナ夫人やまだ幼い長女リュボフィ・長男
フョードルとも見(まみ)えることができるだろう。
N氏の声が耳に入ったらしく、その瞬間、彼はその後ろ姿のままビクッとした様子を見せたが、少しばかり間(ま)を置いたあと、ゆっくりと上半身と首をねじらせて、声の主(ぬし)の方へと振り向いた。
「また現れたか小悪魔クン! 君たちの話は聞きたいが、ワシ(=自分)は君たちの煽(おだ)てや誘いなぞには乗らんぞ!」
ゆっくり振り向いた彼は、相手の姿が視界のスミに入る前に、そう言い始めた。
と、その時、N氏の眼前も耳も口も塞がれた。そしてさらに何人かに後ろから首を締められ羽交い締め(はがいじめ)にされた。その相手の手のひらと腕と胸の感触から、自分が悪霊たちに襲われていることをN氏は直感する。
―― うう、苦しい、、、残念だが、戻るしか手はない。
例の如く心に念ずる。すぐに解き放たれ、場所と時を超え、元の場所・時代へと戻っていくまでの間、N氏は、次のようなことを思いながら、二、三度、ゴホゴホと咳き込んだ。
‥‥予期してなかった事態であったが、自分が悪霊たちに襲われたということは、氏も先ほど彼らに向けて言葉を投げ付けたように、あの深夜の書斎には悪霊たちが強力に蠢(うごめ)き跳梁(ちょうりょう)しているということだろう。一方で、没頭している後ろ姿の氏の周りには、天使や神々が取り巻いて愛とエナ ジーを吹き送っているかのような温かい神々しいアウラ(=オーラ)があった。今回は氏の尊顔を拝することは逸したが、彼の小説の工房
たる深夜の書斎では創造神としての天使たちと悪魔・悪霊たちとが鬩(せめ)ぎ合っているということが知れただけでも収穫であった。
( 最初の探訪・完 )
※最初の探訪早くも完!
……………………
【語注】
※注1
1879年5月は、前月の10日には『ロシア報知』編集部へ『カラ兄弟』の第五編1‐4章を送付し、続きの5‐7章(第5章は「大審問官」の章)を執筆していた時期。
※注2
行く前にN氏が参考にしたドストエフスキーの書斎を映した写真は、「るーじん」さんのページ「ドストエフスキー記念館」に掲載の部屋の中を写した2枚の写真。
アパートの写真や各部屋の内部の写真は、こちらのページでも見れる。
当時の住まい
アパートの二階の10号室
(部屋の数は6部屋)
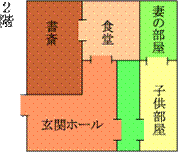
10号室の見取り図

ドストエフスキーの書斎
( 左は本棚。右にあるのがドア。)
上の第1話ではN氏は上の見取り図では書斎の右下の隅(壁に接しているソファーの右)に現れたことになります。
※注3
書斎には机の向こう側の
テーブルに置き時計があり。
※注4
『カラ兄弟』の執筆・送付の時間帯
「ロシアの大学生は殆ど規律を弁えていなかった。時間構わずに私の父のところへやってきては、仕事の邪魔をした。彼らを迎えるのを拒んだことのないドストエフスキイはやむなく夜執筆せねばならなかった。以前でも、大事な章にとりかからねばならない時には、好んで周囲の世界が寝静まっている時刻に創作した。後には、そんな仕事の仕方が習慣になった。
ドストエフスキイは朝の四時か五時迄書き、十一時過ぎにようやく起きた。彼は書斎で寝椅子の上に寝た。
―途中、省略―
朝食が終ると、父は部屋に帰って、すぐさま前夜創作した章を口述するのだった。母はそれを速記し浄書する。ドストエ
フスキイがその浄書を推敲し、それに屡々(しばしば)沢山の枝葉をつけ加える。母はもう一度それを浄書し、印刷所に廻(まわ)す。こうして、彼女は夫の労力を大いに省いたのだった。若(も)しドストエフスキイの妻が速記を学ぼうという考(かんがえ)を起さなかったら、彼はあのように沢山(たくさん)小説は書けなかっただろう。」
(エーメ・ドストエフスキー著
『ドストエフスキイ伝』より。)
※、
なお、作中では、ドストエフスキーの会話も含め、登場人物の会話はすべて日本語訳された現代日本語で行われるとします。
【参考】
※、
『カラマーゾフの兄弟』(光文社古典新訳文庫)の、
・第5編5「大審問官」(巻2・そのp281)
「われわれの仲間はおまえでなくて、きゃつ(悪魔)なのだ、これがわれわれの秘密だ!」(米川正夫訳)
・第7編1「腐臭」(巻3・そのp29〜p32)
「「悪霊はわたしが退治してやる!」 彼は四つの方向に順に体の向きを変え、庵室の壁と四つの隅に、手で十字を切りはじめた。」
・第11編2「小悪魔」(巻4・そのp205)
「わたし、ちょくちょく悪魔の夢を見るの。夢みたいなの。ろうそくをともしながら部屋にいると、急にいたるところに、それこそ部屋の四隅に、悪魔があらわれるの。」
・第11編9「悪魔。イワンの悪夢」(巻4・そのp402)
「悪魔さ! あいつがおれのところへ押しかけてきたんだ。二度来たよ、三度かもしれない。」
※、
「悪魔がそこにいる」
(萩原朔太郎が病床で最後に言った言葉 )
「はて、自分は二流の悪魔らしい。悪をなさんと欲して、かえって善をなす。」
「 自分は、つねに悪をなさんと欲して善をなす、あの力の分身です。」
(ゲーテ『ファウスト』の中の悪魔メフィストーフェレスの言葉 )
「悪魔は我々を誘惑しない。悪魔を誘惑するのは我々である。」
(G・エリオットの言葉 )
※、
「私の場合でも、ある場面が頭に思い浮かぶが早いか、待ってましたとばかり、心に浮かんんだままに書きくだします。それですっかり嬉しくなってしまうのです。さてそれから、数ヶ月、あるいは一年もかかって、それに手を加えます。つまり私はその場面について、一度だけではなく、何度でもインスピレーションを受け直すのです(なぜならば、私はその場面を愛しているからです)。これまでずっとやってきたように、私は何度でもここを
削ったり、あすこへ付け加えたりするのです。そして、正直な話、ずっとよいものができあがります。もちろん、これはインスピレーションがあっての上です。インスピレーションがなくては、なにひとつできるものではありません。」
( 1858年5月31日付けの兄ミハイル宛の手紙より )
「芸術家とはつねに自分に耳を傾け、自分の耳に聞こえたことを自分の心の隅っこに 率直な気持ちで書き留める熱心な労働者である。」
( ドストエフスキーの言葉 )
※、
「創造を志す人は催眠術者と被術者のひとり二役をになわなければならない。」
(シャルル・ボードレールの言葉)
「ニーチェは、霊感に見舞われて忘我の状態で一気に書き上げたという『ツァラトゥストラ』について、「(書く過程で)自分は全く選択しなかった!」と述べている。」
(西尾幹二『ニーチェとの対話
― ツァラトゥストラ私評』より)
※、
「神と悪魔が闘っている。そして、その戦場こそは人間の心なのだ。」
(『カラマーゾフの兄弟』第3編第3 )
※、
「要するに、聖性は悪魔とのせめぎあいのなかか らしか出てこない。」
( 亀山郁夫『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』より )
※、
「ドストエフスキーはわれわれに神をたたえてやまない。だがそれと同時に、ドストエフスキーの文学は悪魔の文学であるというのも、ひとつの常識になっている。つまり読み方によっては、読者は神を求めずにはいられないようにもなれば、悪魔の思うつぼにはまることにもなるということであろう。」
( 小沼文彦著『ドストエフスキーの顔』より )
「彼(=ドストエフスキー)は自分にとり憑(つ)いた悪霊どもを小説のなかで形象(けいしょう)化してそれらを一つずつ祓(はら)う。」
( ルネ‐ジラール著『ドス
トエフスキー ― 分身か
ら統一へ』より )
「ドストエフスキーは厖大(ぼうだい)な「作家ノート」を残している。その克明な記述によっても、彼が謎めいた夢遊の状態で書いたわけではないことはあきらかだろう。にもかかわらず、ドストエフスキーほど、心霊術でいう「霊媒」の助けをかりて書いたにちがいない、といった印象を与える作家はいないのだ。彼の作品は、聖者にとっての「黄金伝説」とひとしく、みえざる天使が口述筆記をしたかのようだ。しかし同時に、そこにはまたしばしば、しごく(=たいそう)人間的な顔がまじりこみ、突如としてなまみのドストエフスキーが顔を出す。」
( 池内紀・筆「最後のビ
ザンチン人」より )
|
![]()
![]()