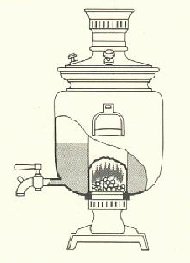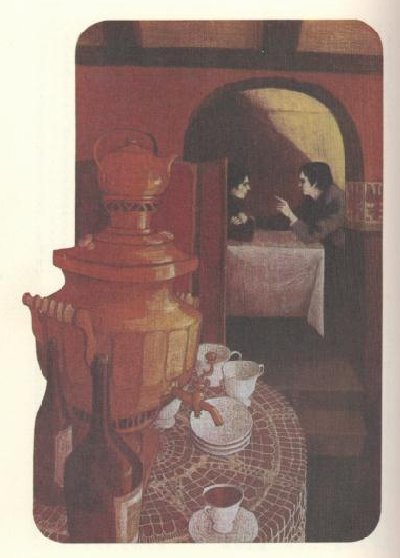|
�P
���V�A�̉ݕ�
�����̉ݕ��Ƃ��ẮA
��������݁E
���݁E����
���������B
�����́A
�P���[�u�����P�O�O�R�y�C�J
�����Ƃ��ẮA
�ȉ��̂悤�ɐF��������
�Z��ނ̎������������B
�P���[�u������ (���F)
3���[�u������ (�ΐF)
5���[�u������ (�F)
10���[�u������ (�ԐF)
25���[�u������ (�D�F)
100���[�u������ (���F)
���A�����̂P���[�u������

�P���[�u������
( ���V�A��1865�N����
���́B���̗��ʁB)
[�ʐ^�F�r�d�j�h�m�d����]
��݁E���݁E�����Ƃ��ẮA
�ȉ��Ȃǂ��������B
���[�u�����
(�P.5���[�u����݁E
1���[�u����݁A�Ȃ�)
�R�y�C�J���
(50�R�y�C�J��݁E25�R�y�C�J��݁E20�R�y�C�J��݁E15�R�y�C�J��݁E10�R�y�C�J��݁E5�R�y�C�J��݁A�Ȃ�)
�R�y�C�J����
(20�R�y�C�J���݁E5�R�y�C�J���݁E3�R�y�C�J���݁E2�R�y�C�J���݁E1�R�y�C�J���݁E1/2�R�y�C�J���݁E1/4�R�y�C�J���݁A�Ȃ�)�A
���[�u������
(5���[�u�����݁E3���[�u�����݁A�Ȃ�)
���A���݂́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A�قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��B
��
�u���V�A�R�C���W�v
(�T����̃y�[�W)
���A1���[�u���ƌ����A�ӂ��A�������w���B�����A���[�u����݂́A���[�u�������ɔ�ׂāA3.5�{��x�̉��l���������B���2���[�u���Ǝ���1���[�u���ł́A�����A8���[�u���ƂȂ�B
������1���[�u��(1�R�y�C�J)�́A���݂̓��{�ł͂�����ɂȂ邩�A�ɂ��ẮA
���A��10000�~(��100�~)
���A5000�~�`10000�~(50�~�`100�~)
���A��5000�~(��50�~)
���A2200�~�`2700�~(22�~�`27�~)
���A��1000�~(��10�~)
�Ȃ��̂������̐�������B
���A�~�ւ̊��Z�͍�����������A�]��쎁�͎����|���w�߂Ɣ��x(�����Е���1966�N����)�̉���ŁA������1���[�u��(1�R�y�C�J)�́A����(1960�N�㔼��)�̓��{�ł́A��1000�~(10�~)���Ɗ��Z���Ă���B1960�N�㔼�ɔ�ׂĂ̌��݂̕������l�����Ċ��Z����Ȃ�A���݂ł́A��L�̂����A���E�����L���Ƃ̂��ƁB
�Q
�o��l���̐����E�ď�
���V�A�̏�����ǂޏꍇ�A�����������̂��A�o��l���̖��O�̋�ʁB���O���̂�������ɁA�����ɌĂׂΖ����O���сA�܂��A�n�̕��Ɖ�b���Ƃł͌Ăѕ����قȂ邱�Ƃ������āA�o�������ʂ����肷��̂ɁA�ǎ҂́A�n�I�A���E��J����B
�o�Ă���e�o��l���̖������p���Ƀ������A�{�ɂ͂���ł����āA�K�X���m�F���ǂ݂����߂Ă����A�Ƃ����̂��A����@�B
�Z���V�A�ɂ����閼�O
���V�A�ł́A���O�́A
���O�S�̂������������Ƃ��ẮA
���E���́E��
�̎O���A���̏��ɕ��ׂČ����B
��F
�A���N�Z�C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t(���J���}�[�]�t
(�J���}�[�]�t�Ƃ̃t���[�h���̑��q�A���N�Z�C�A�̈�)
�������e�������̎q���ɂ���Ăі��B
���V�A�ł��A���̓L���X�g���̐��l��V�g�ȂǂɗR��������̂������āA�唼�̓|�s�����[�Ȃ��̂�������B
��F
�C���@��(�C����)�������̎g�k���n�l
�s���[�g�����g�k�y�e��
�p�[���F�����`���҃p�E��
�A���h���C���C�G�X�̒�q�A���f��
�~�n�C������V�g�~�J�G��
�j�R���C���M���V����̃j�R���E�X
���́A
�j�Ȃ�A
�{���X�A�~�n�C���A�Z���Q�C�A�E���W�~�[���A�j�R���C�A���[���[�A�A���N�T���h���A
���Ȃ�A
�i�^�[�V���A�J�`���[�V���A�j�[�i�A�K���[�i�A�G���[�i�A�^�`���i
�Ȃǂ��L���B
����
�����e�������玩���I�ɂ�������́B
���q�Ȃ�A�u�`�����B�`(���B�b�`)�v�ȂǁA���Ȃ�A�u�`�����i�v�ȂǁA�ƂȂ�B
(���̓I�ɂȂ�B)
��F
�h�X�g�G�t�X�L�[�̏ꍇ�A���e�̖��́u�~�n�C���v������A�u�~�n�C�����B�`�v�ƂȂ�B
��
���ƌn�̌Ăі��B�u�h�X�g�G�t�X�L�[�v�́A���łȂ��āA���ł���B
�u�`�X�L�[�v�u�`���t�v(�u�`���t�v(���̓I�A���̓G��)�̌`���|�s�����[�B
���́A�L���X�g����V�A�ɂ����鐹�l�E���̖���n������o�������̂������B
��F
�y�g���[�t���g�k�y�e��
�h�X�g�G�t�X�L�[������̐�c���Z�y�n�̑����h�X�g�G�[���H
�����̏ꍇ�A�u���v�̌���́A
�u�`���v�̌`�ȂǂɂȂ�B
��F
�\�[�t�B���E�Z�~���[�m
���i�E�}�������[�h
��(���}�������[�h�t)
�Z���́A�ڏ�
����
�����e��e�����F�l�̊Ԃ����Ŏg����Ăѕ��B
���̌�����A�u�`�[�����v
�u�`�[���`�J�v�u�`�[�j���v
�Ȃǂɕς��āA�ĂԁB
(���̓C�A���̓G�ɂȂ�B)
��F
�A�����[�V��(���A���N�Z�C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t)
���[�W��(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)
�\�[�j���A�\�[�l�`�J(���\�[�t�B���E�Z�~���[�m���i�E�}�������[�h��)
�K�[�j��(���K�����[���E�A���_���I�[�m���B�`�E�C���H���M��)
���̍ŏ��̕�����
�����ČĂԈ��̂�����B
��F
�~�[�`���A�~�[�`�J(���h�~�[�g���C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t)
�h�D�[�j���A�h�D�[�l�`�J(���A�u�h�[�`���E���}�m���i�E���X�R�[���j�R��)
�ڏ�(�̏�)
����������y�̂����Ăѕ��B
���������ŁA���̌�����u�`���J�v�Ȃǂɕς�����A���̍ŏ��̕����������肵�āA�ĂԁB
��F
�K���J(���K�����[��)
���@���J(���C���@��)
�Z��X�̗p����
�E�e���q���ĂԂƂ���A�v�w�E�Z��o���E�e�F�ǂ����Ȃǂ̂悤�ɂ����e�����ԕ��Ō݂����ĂԂƂ��ɂ́A�������ŌĂԂ��A���̏ꍇ�A�����Ă�������p�����B
�E�e�����Ă��ڏ�̐l�≓���������Ęb���ԕ��̐l���ĂԎ��́A���͂����u���E�����v�ŌĂ��̂��ӂ��B
��F
���W�I���E���}�k�C�`(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)
�E�����̒��ł́A��҂��A�n�̕��œo��l���ɂ��ďq�ׂ鎞�ɂ́A�u���v�A���ɁA�u���E�����v�Ŏ����B
��F
���X�R�[���j�R�t(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)
�p�[���F���E�p�[�������B�`(���p�[���F���E�p�[�������B�`�E�g���\�c�L�[)
�i�X�^�[�V���E�t�B���|���i(���i�X�^�[�V���E�t�B���|���i�E�o���V�R�[��)
(���M��̓��{��\�L�Ƃ��ẮA�u�i�X�^�[�V���E�t�B���|���i�v�Ƃ��Ă�����̂�����)
�R
�g���E���E��
�M���݈̎�
(���݁A���݁A�j��)
�E�s���[�g���ꐢ(�݈�1682�N�`1725�N)�̑�ȑO�ł́A���V�A�ł́A�M���݈̎ʂƂ��ẮA�u�����v�����Ȃ��������A�s���[�g���ꐢ�́A�M��(�g�{�������X�g�{)�݈̎ʂƂ��āA���݈ȊO�ɁA�u�����v�u�j���v��V�݂��A���̎O�݈̎ʂ́A1917�N�̃��V�A�v���܂ő������B
(�Ȃ��A���{�̖������{����߂����E��E���E�q�E�j(���قǍ���)�Ƃ����ؑ��݈̎ʂ́A�C�M���X�̏㋉�M���݈̎ʂɂȂ�������́B)
�S�̂Ƃ��ẮA�݈ʂ̂Ȃ��M���������������A�Â��ƕ��̋M����Ƃ��Ɍ��т̂������M���ɂ́A�u�����v��u�����v�݈̎ʂ��^�����A�o���g�C���݂̏o�g�̃h�C�c�n�M������ƉƂɂ́A�u�j��(baron)�v�݈̎ʂ�������ꂽ�B
�E�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A
�w���s�x��
���C�V���L�����݁A
�Z(�V�`���[)���݁A
�w�s����ꂽ�l�тƁx��
�����R�t�X�L�[���݁A
�w�����N�x��
�Z���Q�C�]�y�g���[���C�`���݁A
�j�R���C�V���݁A
�ȂǁA���V�A�̍ŏ㗬�̖���̋M���ł������݉��̓o��l�����悭�o�Ă���B
�w���s�x�̃��C�V���L���́A���������V�A�̑����Ȗ���̐��P�M���̖���(�܂���)�Ƃ݂Ȃ��Ă��āA����u���C�V���L�����݁v�Ɩ�����Ă���B(�V�����ɂ̏㊪��p12)
�w�����N�x�ł́A�A���J�[�W�C(�A���J�[�W�C�E�}�J�����B�`�E�h���S���[�L�[)�́A�����̐��h���S���[�L�[�𖼏�������A���肩��u���݂̃h���S���[�L�[�����H�v�ƕ�����āA(���V�A�ɂ́A�h���S���[�L�[�ƂƂ�������̌��݉Ƃ��������B)�u����A�����̃h���S���[�L�[�ł�(�_�z������̉��j�̑��q��)�B�v�ƕ����������Ɍ����ӏ�������B)
�j���Ƃ��ẮA
�w�����N�x��
�r�I�����O�j��
�ȂǁB
�Ȃ��A�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A��v�o��l���Ƃ��ẮA���݂̐g���̐l���͓o�ꂵ�Ă��Ȃ��B
(�g���X�g�C�̏����ł́A���݉Ƃ̐l�����悭�o�ꂵ�Ă���B)
�����E�����̊K�ʁA�`����
�鐭���V�A���̊������ł́A
�����́A
�P�����`�P�S����
�̊K�ʂ�����A
�����́A
�E�����A�叫�A�����A�����A�㏫�A
�E�卲�A�����A�����A
�E���сA���сA�O�����сA
�E���сA���сA���ѕ�
�Ƃ����������P�S�̊K�ʂ��������B
��������ނ��������̊����́A
�ޖ��`�A�`���R
�ƌĂꂽ�B
���шȏ�����Z�ƌĂԁB
��
�w�J���Z��x��
�E�ޖ����
�̃X�l�M�����t�A
�E�ޖ����Z
�̃h�~�[�g���C
�w�߂Ɣ��x��
�E�X����(�����ł͑��тɂ�����)
�̃}�������[�h�t
�ȂǁB
�u�`���R�v�Ƃ����Ăѕ�
�w���s�x��
�C���H���M�����R�A
�G�p���`�����R
�Ȃǂ́u�`���R�v�Ƃ����Ăѕ��́A���R�l�������l���A�R�E����ނ�����(�ސE��)�ɂ��A���_�Ԃ��Đ��̉��ɕt���Ă�����̂ŁA�R���ŁA������x�R�������������R�l(�R���ł́A������R�����w������Ȃǂ́u���R�v�Ƃ������ʂɂ������킯�ł͕K�������Ȃ��B)�Ƃ����Ӗ��������Ă���B
�����ł́A�ނ�R�l�̒��ɂ́A�ݐE�����珬�������߂āA���̂��߂������őސE��ɃA�p�[�g��q��Ȃǂ̌o�c���s���҂����āA�ނ�́A���̑��̐l���ɂ����āA�u�`���R�v�Ɩ�����ĐV���Ȏd���ɏ]�����A���̐l����������Ăꂽ�A�Ƃ����ʂ��������B
�w���s�x��
�G�p���`�����R�A
�w�q���ҁx��
���R�A
�Ȃǂ́A���̗�B
����A
�w���s�x��
�C���H���M�����R
�́A�R�E��ނ��Č�́A�d���������ɏ�(�߂���)�������ē��X���ɂЂ����Ă���A�����V�l�ł���A���R�l�ł��������Ƃ̖��_��l�ɂЂ��炩�����߂ɕt���Ă���Ăѕ��ɉ߂��Ȃ��B
�S
�e���u���N
(�X�V�F26/02/04)
[����]
�E�e���u���N
�y�e���u���N�ɂ���
�E����A�C��
����
����
�E��A�^��
���l���@��
�^���A���X
�E�����A�X����
�����Z��
�ʑ�
���A���L
�E�ݔ�
�������A����
�X��
�E�X
�������A������
����
����
�E�L��A����
���Z���i���L��
�E�{��
�w�Z
��q���A����
�E��蕨
�n��
�S��
���@�@�@���@�@�@���@�@
�y�e���u���N�ɂ���
�o���g�C�ւ̐i�o�̂���1700�N����n�܂����X�E�F�[�f���Ƃ̐푈(�k���푈�E�`1721�N)�ŒD�悵�����n�I�ȏ���Ƒ�X�т̒n�ɁA�����̃��}�l�t���̃s���[�g�����(�݈�1682�N�`1725�N)�̎w���̂��ƁA���[���b�p�ւ̑����J�����ƁA1703�N�ɊC�`�Ɨv�ǂ�z�����������s�s�y�e���u���N�̋N���B�����́A�s���[�g�����̖��Ɛ��g�k�y�e���̖��ɂ��Ȃ�ł���B
�l���@��̂��̃f���^�n�����[���b�p���̐l�H�s�s�̌��݂͐i�݁A1713�N�ɂ́A���������̊����������āA��s�����̓s�s�Ɉړ]���ꂽ�B
�ȗ��A���V�A�v���̗��N��1918�N�Ƀ��X�N���Ɏ�s���ڂ����܂ŁA���V�A�鍑�̎�s�Ƃ��āA���V�A�̐����E�o�ρE�����̒��S�ƂȂ��Ĕ��W�����B
(�s���́A1914�N�Ɂu�y�e���u���N(�T���N�g�E�y�e���u���N)�v����u�y�g���O���[�h�v�ɁA1924�N�ɂ́u���j���O���[�h�v�ɁA1991�N�ɂ͋����́u�T���N�g�E�y�e���u���N�v�ɖ߂��Ă���B)
��s�ړ]���ɂ�10���l(���̑����̓��X�N������̋����ڏZ)�������l���́A1800�N�ɂ�22���l�ɂȂ�A�H�Ɖ��E���{��`�����i��19���I�ɓ���Ɣ���I�ɑ������A�S���̊J�ʂ�1861�N�̔_�z����̂̂��́A�H��J���҂Ƃ��Ă̒n���̔_���̈ړ��������A�w�߂Ɣ��x�����������N�̑O�N��1865�N�ɂ�54���l�A�h�X�g�G�t�X�L�[���S���Ȃ����N�̑O�N��1880�N�ɂ�84���l�A1900�N�ɂ�150���l�Ɋg�債�Ă���B
�s�̖ʐς́A�����s��̖ʐς�57���B
�����̎s�S�̂́A�ȉ��Ő��肽���Ă���B
�암��
�E�{�y�A
�{�y�̖k������
�E���V���G�t�X�L�[���A
�k����
�E�y�e���u���N�X�L�[��
(�y�e���u���N��)�A
�����߂Ƃ����召�̎��̓�
(�s�X��101�̓���
�킩��Ă���B)
�k���́A
�E���B�{���O��
���̊Ԃ�������Ƃ��āA
�암�̖{�y�̖k���烔�B�{���O�X�L�[��̓쑤�𗬂��
�E��l���@���A
�{�y�̖k�����̃��V�[���G�t�X�L�[���Ɩk���̃y�e���u���N�X�L�[���̊Ԃ𗬂��
�E���l���@��A
�{�y�̒������𗬂��
�E���C�J��
�ȂǁB
�^���Ƃ��āA
�{�y�̖k������쐼�ւƑ���A
�k���́A
�E�G�J�`�e���[�i�^�́A
�쑤��
�E�t�H���^���J�^��(�t�H���^���J��)
����
�E�t�B�������h�p
�ɖʂ���B
�s�X�́A�l���@��̉͊y�т��̃f���^��ɍL�����Ă��āA�s�̖�15���͐��ʂł���(�앝��340m�`650m�ƍL��)�A�l���@��͎s���ɓ���ƁA�������̎x���ɂ킩��A�^�͂��s�X���c���ɑ����Ă����A�s���ɂ́A600�߂��̋����������Ă���B
(���������_�ŁA�y�e���u���N�́A�������u���̓s�v�ł���A�u�k���̃��F�j�X�v�ƌ�����䂦��ł���B�h�X�g�G�t�X�L�[�̑̌��ɂ���悤�ɁA�Ă̔���̃l���@��̂قƂ�ɗ��ĂA���z�I�ȃp�m���}��̌����邱�Ƃ��ł���B)
���Ƃ��ẮA
�암�̖{�y�Ɩk�����̃��V�[���G�t�X�L�[�������ԋ��Ƃ���
�E�j�R���G�t�X�L�[��(���j�R���C��)�A
�E���{���A
�암�̖{�y�Ɩk���̃y�e���u���N�X�L�[��(�y�e���u���N��)�����ԋ��Ƃ���
�E�g���C�c�L�[��
���m����B
�s�X�̌����́A�������A�s���[�g�����̕��j�Ɋ�Â��A�Α���̌�������������B
���H���������A�ŕܑ�����A
�{�y��k������쓌�ɑ���ڔ����ʂ��
�E�l�t�X�L�[��ʂ�A
��k�ɑ���
�E���H�Y�l�Z���X�L�[�ʂ�
�𒆐S�ɁA�e�ʂ肪�c���ɑ����Ă���B
�w�߂Ɣ��x�ɓo�ꂵ�Ă���A
�E�Z���i���L��
(�G�J�e���[�i�^�͂̓쑤�̋��)
�́A�{�y�̒����Ɉʒu���A�s�O����̈ړ������W�܂鏎���̎s��Ƃ��ē�������B
�Z���i���s���т́A�l���̉ߖ����ł���A���݂��̋����Z��r�������W���A����⏩�ƂȂǂ����������B
�Z
�y�e���u���N�ɂ��āA����
�������E�Љ�Ă���{
�����݁A�s�̒��̂��́B
a(�����̃y�e���u���N��
���āA���낢�����E��
��������)
1.
�u�w�߂Ɣ��x�̃Z���i���L��E�G�v
�k�w�m��ꂴ��h�X�g�G�t�X�L�[�x(�������V��B��g���X1993�N���ŁB)���ɏ����Bp51�`p87�B�l
�����̃y�e���u���N�́A�l���E�g���ʐl���E�Z����E�����H���E���ƁE��w���E�l�G�̗l�q�E�Z���i���L��E���R�A�Ȃǂ��Љ�Ă���B
2.
�u���z�s�s�y�e���u���N�v
�k�w�h�X�g�G�t�X�L�[�E�m�[�g�\�u�߂Ɣ��v�̐��E�x(�����F�����B��B��w�o�ʼn�1981�N���ŁB)��
�ɏ����Bp281�`p296�B�l
�w�߂Ɣ��x�̕���Ƃ��Ẵy�e���u���N�ɂ��ĊȌ��ɏЉ�Ă���B
3.
�u�h�X�g�G�t�X�L�[�̃y�e���u���N�v
�k�w���z�h�X�g�G�t�X�L�[�x(�������F���B�ߑ㕶�|��1997�N���ŁB)���ɏ����Bp55�`p81�B�l
�N���ȍ~�̑唼���y�e���u���N�ɋ������܂����h�X�g���̏Z����(�p�ɂɋ���ς����A����18�̓]����)�̊X����Ȃǂ��A���ɏЉ�Ă���B
4.
�w�h�X�g�G�t�X�L�[⼌��ƏȎ@�x
(�������F�Җ�B������1985�N���ŁB)�̒���
�u�y�e���u���N�v�̍��B
�y�e���u���N�ɂ��Č��y���Ă���h�X�g�G�t�X�L�[���g�̌��t���W�߂��Ă���B
5.
�w����v�z�\���W��
�h�X�g�G�t�X�L�[�x
(1979�N9�����B�y�Њ��B)�ɏ����́A
�u���낵����̒��y�e���u���N�v(���r���E�M)
�u�y�e���u���N�̃t���k�[���i���U��ҁj�v(�C��O�E�M)
�u�y�e���u���N�����̒��̓s�s���v(���q�E�M)
�u�s�s�\�h�X�g�G�t�X�L�[�ƔM������v(�W�����O�E�M�A�u�V�Ö��)
�u�s�s�ƕ��w�\�Θb���h�X�g�G�t�X�L�[�ւ̐V���������v(�O�c���Ɛ�[���j���̑Βk)
b(�y�e���u���N�̍��́E
�؍L�E�ό��ē�)
1.
�w���y�e���u���N�x
(��Ή�F���B������1996�N���ŁB)��
�Í��̃��V�A�̕��w��|�p�ɂ�����y�e���u���N�̂��Ƃ��Љ�Ă���B
2.
�w�T���N�g�y�e���u���N
���ׂƌ��z�̊X�x
(���c�d���B1996�N���{�����o�ŋ���ŁB)��
�M�҂̃T���N�g�y�e���u���N�؍�(1995�E1996�N)�̋I�s�G�b�Z�C�B�y�e���u���N�̍��̂��A�v�[�V�L���E�S�[�S���E�h�X�g���Ȃǂ̍�i�ɂ����y���A�Љ�Ă���B
3.
�u���j���O���[�h�v
�k�w�\���F�g���s�ē��x(�����V���B��X����Y���B1966�N���ŁB)�ɏ����Bp104�`p152�B�l
���j���O���[�h(�T���N�g�y�e���u���N�̋���)�̉��v��e�������ē����Ă���B
4.
�r�f�I�w���V�A�̕��
�X�N���E���j���O���[�h�x
(�������E(��)���Y�t�H�B
�J���[�̓��{��ŁB)��
����
(�тႭ��A�͂���)
�y�e���u���N�͈ܓx������(�k��60�x��)���߁A���Ĉȍ~��5���`8���ɂ͔���ƂȂ�(�s�[�N��6�����{)�A���̊��Ԃ́A���z�͌ߌ�11�����ɒ��ނ��A�ǂ��Ղ�������Ă��܂����Ƃ��Ȃ��A�^�钆�ł������̂܂܂ƂȂ�B
���Ȃ݂��A�~�͒����Z���āA�~�����߂Â��ƌߌ�4���ɂ͖�ɂȂ�B
���A�����̒��̔���
�ɂ��Ă̋L�q
�w�n�����l�тƁx
�u���������A�킽�������݂̂Ƃ���ւ������т��т������͂����Ȃ����Ⴀ��܂��H���A�����ł��傤�H�Ŗ�ɂ܂���ĔE��ł����Ƃ�����ł����H����ɑ��A�߂���͖�炵������Ȃ����Ⴀ��܂��B���܂͔���̋G�߂Ȃ̂ł�����B�v
(�W�F�[���V�L����5��20���̎莆���B�V�����ɂ�p37�B)
�w�߂Ɣ��x
�u�ނ�͒��납������āA�l�K�ւ̂ڂ��čs�����B�K�i�͏�ɍs���قǁA�Â��Ȃ����B�����قƂ�Ǐ\�ꎞ�߂��ŁA���̍��y�e���u���N�͔���̋G�߂Ƃ͌����A�K�i�̏�̂ق��͂Ђ��傤�ɈÂ������B�v
(��1����2�B�V�����ɂ̏㊪��p43�B)
�w����x
�u���͎������̎O�x�ڂ̃����f���[�������A�������̎O�x�ڂ̔��邾�����B�v
(�p�앶�ɂ�p76�B����́A����̎����ɂ�����5���Ԃɂ킽�镨��ɂȂ��Ă���B)
�T
�N���s���E���j��
(�X�V�F26/02/04)
( �j�Փ� )�@�@�@�@�@�@�@
�Z ���[���J�Ղ�
�@
12��25���ȍ~�A���[���J(�����w(�Ƃ���)�ƌĂ�郍�V�A�̃N���X�}�X�c���[�B�~�a�Վ��B) �̏���t�����{�i�����A12��31���ɏ����������A1��7�����~�a��(���V�A�����̃N���X�}�X) ���o�āA1�����܂ő������V�A�̃N���X�}�X�̍Ղ�̂��ƁB
���V�A�ł�12��25������1��6���܂ł�12���Ԃ��u�N���X�}�X�T���v�Ƃ��Ă���B
���[���J�̏W���ɂ́A���V�A�̃T���^�N���[�X�ł����}���[�X�ꂳ�����X�l�O���[�`�J(�ᖺ)���o�ꂷ��B
�k�Z�ҁw�L���X�g�̃����J�ɏ����ꂵ���N�x�l
�Z ������
( ���V�A��ł́A�p�[�X�n )
�\���˂ɂ�����ꂽ�L���X�g���O����ɕ����������Ƃ��������j�����B
���Ă̕�����(�C�[�X�^�[)�Ɠ������A���V�A�ł��A�u�t���̎��̖����̌�̓��j���v�ɍs����B
�ړ��j�Փ��Ƃ��āA�N���Ƃɕ����Ղ̓��͈قȂ邪�A��̊W�ŁA�J�g���b�N��v���e�X�^���g�̂�����ꃖ���قǒx���A��́A3���㔼����4�����ɂ����Ă̎����ɍs���A�t�̓�������яj���t�Ղ�Ƃ��Ă̐��i������B
���V�A�����ł́A�C�G�X�̏\���˂̌Y�ɂ��߂̏��������A�C�G�X�̎O����̕������u�C�G�X�̏����v�Ƃ��ďd������̂ŁA�����Ղ́A���V�A�����̍ő�̍Փ��ł���A���ʂȈӋ`��L
������B
�����Ղ̑O���0���ɂȂ�ƁA�i�ՂƏW�܂��Ă����M�҂����̑�\������̉����A�u�n���X�g �X(���V�A�����ł̃L���X�g�̌Ăі�)��������v�Ȃǂ̎]���������������u�\���s�v��
�s���A���̂��ƁA����̒��ŁA�����܂Ŗ��O���ė������܂�(�����̋���ɂ͊�{�I�Ɉ֎q�� �Ȃ��B)�F��(���Ƃ��B���̂��̂����Ƃ����S�B)���s���B��������ƁA�u���̗�V�v���s���A �M�҂����������������(���͕����̏ے��Ƃ����)�E�N���[�`(�~���`�̃p���P�[�L)�E�p�[�X�n(�����p�̃`�[�Y�P�[�L)�Ȃǂ��������H���āA�C�G�X�̕����̊�т��������B
�@�@�@�@�@
�@
�Z ���
( �������̂��݁A�l�{�ՁA
�l�{�ցA�l�{�߁A
���V�A��ł́A�|�X�g )
�����Ղ��}����O��7�T��(���(�����j�A������)��������40����)�̏������Ԃ̂��ƁB
�C�G�X���H�ו������ݐ����Ȃ��Ɉ����̗U�f���Ȃ���r��ʼn߂�����40���Ԃ̋ꂵ�݂��������Ƃ����Ӗ�������A���̊��ԁA�M�҂́A�ؐH�ɓ���A���ʂȋF��̋�������A
��(���̂���)���E���i���ĉ߂����B
�����Ղ̑O�̈�T�Ԃ��u���T��(�_���T��)�v�A�����Ղ̏T���u�����T���v�ƌ����B
�k�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̑�6�ґ�2�̃}���P�[���̉�S�̉ӏ��A�ȂǁB�l
�����Ղ̂��Ƃ͏j����40���Ԃ�����A�����Ղ���50���ڂɂ́A�u����~�Ս�(�����O�ҍՁA�{��)�v���s����B
�k�w�߂Ɣ��x�̑�6����6�A�ȂǁB�l
�@
( �l�̏j���� )
�Z ���̓��̏j��
( �������̏j�� )
�����̐��疼�Ɠ������������҂̍Փ��B�a������������ɍs����B
�k�w�����N�x��1���̑�2�͂�1�A�ȂǁB�l
�@
�U
����
[�㒅�A�O���A����]
�E�O���A�z�O��
�E�}���g
�E������
�E�T���t�@��
���V�A�Ō×��A��Ƃ��ď����̒��p�����\�I�������B���ʂ͂����Ԃ���₩�ȁC������W�����p�[�X�J�[�g�`�����Ƃ�B�ʏ�u���E�X�̏�ɒ��p���C��̒Z�����̂�����B
�E���o�V�J
���V�A�̖������̈�B�l�ߋ݁A�����A���O�J���ō���̒j���p��߁B
�E�h���X(���̃h���X)
�E�V���c
�E�u���E�X
[�V���[����]
�E�v���g�[�N
���V�A�̖����I�ȏ����p��蕨�ŁC�G�߂��킸�p������B�ӂ��͎l�p���z��C�܂��̓j�b�g�n�ŁC���ɔ��ق��C���ɂ�������C��Ɋ������肷��B���F�̉₩�ȑ��ʂȉԕ��������D�܂��B
���A�w�߂Ɣ��x�ŏo�Ă���B
�E�V���[��
�E�X�J�[�t
[�X�q�ށA���]
�E�X�q�A���V�A�X
�E�n�b�g(�V���N�n�b�g)
�E�t�[�h�t���̏��
�E�X�e�b�L
[�u�[�c��]
�E���C�A�����C
[�A�N�Z�T���[�A�z��]
�E���l�N�^�C
�E���{��
�E�J�t�X�A�s��
�E�w��
�E�n���J�`�[�t
[��v]
�E�R�r�v�A�q�r�v
��܁A���̗��n�A
�u�[�c�Ȃǂɂ��Ȃ₩��
��v�ȎR�r(���M)�v
���p����ꂽ�B
�E�q����
�V
�Ƌ�E���x�i
[����]
�T�����[��
�E�}�z�K�j�[���̉Ƌ�
�E����
�E����
�E�����v
�E�J���e��
���@�@�@���@�@�@���@�@�@��
�T�����[��
�E���V�A���L���i���p�̓����������B
�E�����ς�Ƃ�������ɖF���������悢�A���̕�������r�I������ɕۉ��̋@�\��������Ă���̂ŁA19���I�ȗ����V�A�l�ɑ傢�Ɉ�����A�H��̏�̃T�����[���͉ƒ�c�R�◈�q���҂̏ے��ƂȂ����B
�E��W�̏���}�{���������g�����Ϗo���A�O���X���邢�����q�ɔ����قǒ����A�{�̂̉�������ˏo�Ă���F(����)���Ђ˂��ĔM���𒍂������̂��ʏ�̈��ݕ��B�������J�b�v�����M�Ɉڂ��Ĉ��ނ̂́A�_���̓`���I�Ȉ��ݕ��B
�E�ޗ��͓����邢�͉����B�~���`�Ȃ����~���`�̗e��̓����Ƀp�C�v�����Ă��Ă���A���̒��Ɏ�Ƃ��ĖؒY�A�Ƃ��ɂ͊������؊��⏼�������߂ĔR�Ă����A�������B

�T�����[��(����61�p)
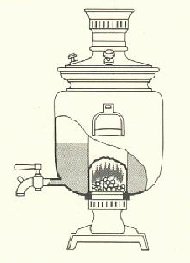
�T�����[���̍\���}
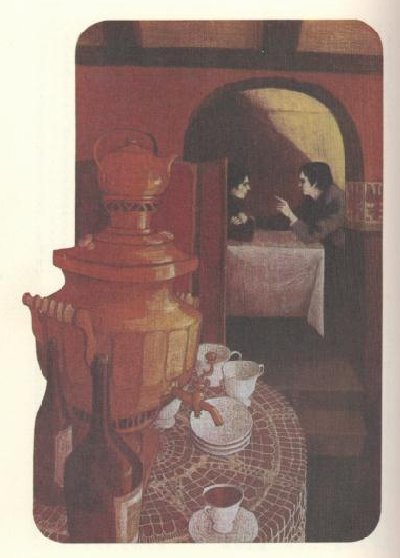
�}���G�̃T�����[��
�W
���H
��
���ݕ�
( ���E�R�[�q�[�� )
�E����(�g��)
17���I�ɂ������A������Ĉȍ~�A���V�A�l�́A19���I����́A�_�Ƃł��A����A�e�ƒ�ɂ����T�����[���ōg�����Ϗo���ŁA����(�g��)���D��ň��B�@
�E�R�[�q�[
���V�A�l�́A�̂���A�g���ƂƂ��ɁA�R�[�q�[���悭���B���V�A�̃R�[�q�[�͔Z�����̂������B
( ����� )
�E�R�j���b�N
�t�����X�����̃R�j���b�N�n���Y�̍����u�����f�B�[�B�������������������̂��A�M�ɋl�߂ďn�������č��B
���A�w�J���Z��x�̃t���[�h���̍D���B
�E�E�H�g�J(�E�H�b�J�E�Ύ�)
���V�A�̑�\�I�ȏ������B���F�����E�������L�ł��邪�A�A���R�[������40�`60���ƍ����B
�唞�E���C���E�����E�g�E�����R�V�Ȃǂɔ���������ē����E���y�������������̂��A�����̖ؒY�ŒE�L�E�h��(�납)���Ă���B
���A�h�X�g�G�t�X�L�[�͒��A���p����������Ȃ���E�H�g�J���������Ɋ܂�ň��ނ��Ƃ��K���������炵���B
�E�r�[��
���V�A�l�́A�×��A�r�[�����D�B���V�A�̌Â�����̃r�[���́A�Y�_�����Ȃ��āA�����Z���̂������ł���B
�E�V�����p��
���V�A�ł́A�V�����p���́A�V�N��N���X�}�X�T�Ԃɂ悭���܂ꂽ�B
�E�|���X(�|���X���A�p���`)
�|���`���̂��ƁB�u�����f�B�[�ɉʕ��̏`�⍻���Ȃǂ����������ݕ��B
�E���N���X
(KBAC)
���V�A�Ɠ��̃R�[���Ɏ������A���R�[�����̎_(��)���ς������������̂��ƁB�Ăɂ悭���܂��B
�ʕ���I���ō����̂Ȃǎ�ނ��F�X���邪�A�ӂ��́A���C����唞�ɍ��p�������Ĕ��y�����č��B
���A�w�߂Ɣ��x�w�J���Z��x�ɏo�Ă���B
�E�Ԃǂ���(���C��)
�E����(������)
�E���L���[��
��
�H�ו�
�k�p���A�p�C�A�p���P�[�L�l
�E�����p��(����ς�)
����n�ł��悭����C���������A�����Ď_��������B�����Ƃ̑������悢�B�X�[�v�ƂƂ��ɐH���郍�V�A�̒�Ԃ̎�H�B���C���p���B
�E���s���[�O
���V�A�̑�^�p�C(�p��)�̂��ƁB���ɋ�����Ă�����̂�����B
�E���u����(�u���k�C)
���V�A���̃N���[�v�܂��̓p���P�[�L(�z�b�g�P�[�L)�̂��ƁB�����n���������������~�`�ɔ��Ă��ɂ��č��B
���(�����Ղ̑O�̎��T��)�̑O�̃o�^�[�Ղ�ł��u���k�B�������������ďj���A�t���}���鏀���������B
�E���s���V�L
��(��)�����������܂�傫���Ȃ��g���p���܂��͓��\��(�ɂ��܂イ)�̂��ƁB
�����������˂Đ��n�����A��Ƃ��āA���⋛�A��ȂǁA�G�߂ɉ��������̂�����B
�E�����\��(�t�B�b�V���E�p�C)
���A�w�J���Z��x�̃X�����W���R�t�������ӂ̗����B
[����]
�E�����A�e����
�E�J�c���c
�E�r�t�e�L
�E���Ⴊ����
�k�n���A�\�[�Z�[�W�l
�E�n��
�E���l��(�\�[�Z�[�W)
�k���l
�E��(�T�[����)�A��������
�E��(�j�V��)
�E�`���E�U��
�E����(�j�W�}�X)
�E��(�X�Y�L)
[�����A�L��]
�E�C�N���A�L���r�A
�E���y(����)
[�O��]
�E���U�N�[�X�J
���V�A�̑O��(�����E�I�[�g�u��)�̂��ƁB���E�ׂȂǂ̖��Ђ��A�L���x�c�̐|�Ђ��A�T���_�Ȃǂ̐��荇�킹�����S�B
[���]
�E�ӉZ(�L���E��)
�E�L���x�c
[�X�[�v]
�E���E�n�[
�`���E�U���A���A�ׂȂǂ̋����g�����X�[�v�̂��ƁB���ł������Ƃ�A��ƈꏏ�ɋ����ςč��B�@
���w�J���Z��x�̃X�����W���R�t�������ӂ̗����B
�E�V�`�[
�L���x�c�𒆐S�Ƃ�����؏`�B�H�ׂ�O�ɃT���[�N���[��������B
�E�{���V�`
�E�N���C�i���˂̑N�₩�Ȑ[�g�F(�r�[�c)�������ύ��݃X�[�v�B
���h�X�g�G�t�X�L�[�̍�i�ł͂قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��B
�E���\�������J
�������������鍁�h���̂�������������Z���X�[�v�B
�E���I�N���[�V�J
�ĂɍœK�̉��g�킸�ɍ���₽���X�[�v�B�L���E����^�}�l�M�A�W���K�C���A�n���Ȃǂ����������č������킹�A����ɃN���X�������č��B
[�W������]
�E�W����
���V�A�ł́A�W�����́A�p���Ȃǂɂʂ��ĐH�ׂ邾���łȂ��A�W�������r(��)�߂Ȃ��炨��������A�g���ɓ���ăW�����e�B�[�ɂ��ĐH�����B�@
���A�w�J���Z��x�ł́A����ڂ̃W�������o�Ă���B
�E�n�`�~�c
�k�����i�l
�E�`�[�Y
�E�X���^�i(�T���[�N���[��)
���V�A���Y�̔��y���ŁA���[�O���g�̈��B���\�������Ƃ��ă��V�A�l�͂Ȃ�ɂł� �����ĐH�ׂ�B
�k�ۑ��H(���Ђ��A�|�Ђ�)�A�Ђ����l
�E�s�N���X
�L���x�c��l�Q�E�L���E���E�g�}�g�Ȃǂ�Ђ������́B
�E�U���[�N���E�g
�L���x�c�̒Ђ����B
[���َq��]
�E�L�����f�B
�E�k�K�[
�\�t�g�L�����f�[�̈��B
�E�h���b�v
�E�����p���V�G(�ʕ�����X����)
�E�p�X�`��
���V�A�̃}�V���}�����َq�B
�E�`���R���[�g
�E�A�C�X�N���[��
�E�p�X�n
�t���b�V���`�[�Y�ō�镜����Ղَ̉q�B
[�i�b�c�ށA�L�m�R��]
�E�N���~
�E�L�m�R
���V�A�l�ɂƂ��ďd�v�ȐH�ו��A�D���B
[�ʕ�]
�E�����m��(�O���[�V��)
�E���Z(�X�C�J)
�E�I�����W
�E�u�h�E�A���[�Y���A
�i�c�����V
�E������
�k�������A���h���l
�E����
�E�X����
�E��
�E�Ӟ�
�E���炵
�k�����l
�E���f�B��
�E�R���A���_�[
�E�p�Z��(�C�^���A���p�Z��)
�X
�@���E�@�h
[����]
�E���V�A����
�E�����h
(�����k�A�ËV���h�A
�ڐg�h�A�����h�A���S�h)
�E���V�A�̐_�X�A
���܂��܂Ȗ��ԐM��
�E��n(��Ȃ��n)�ւ�
�M��(��n�ւ̐ڕ�)
�E�C�R�����q
�E���l�M��
�E����M��
�E�����̃��V�A���
�E�Q�l�ƂȂ�{
�E�T�C�g
���@�@�@���@�@�@���@�@�@��
���V�A����
(�T�v)
�E�����ւƓ`������L���X�g���̓���������(�M���V��������)�̈�Ƃ��āA10���I�ɃL�G�t�ɓ`��胍�V�A�Ō`�����ꂽ���V�A������̋����B���V�A�������14���I�ɂ͂��̒��S�����X�N���Ɉڂ��A�����[�}�鍑���C�X�����̎x�z���ɓ�����16���I�ȍ~�͓���������̒��S�ƂȂ����B���ẴJ�g���b�N���ɑ��ď����̃L���X�g���̎p�⋳����ێ����p�����Ă���Ƃ��Ă���B
�E�勳�E�m���E���V�Ȃǂ̓Ǝ��̐��E�ʁA18���I�ɐ݂���ꂽ�@���@�A�×��̐��l�̗�`�A�C�R��(����)��q�A�Ǝ��̏\���̐���A�Ǝ��̋F���(�����Ē����ԋF�邱�ƂȂ�)�A�\���˂Ŏ������L���X�g�Ƃ��̕������ւ̏d���A�Ǝ��̏j���̎d���A�X�C�^�i�l�M�V��^�j�̃h�[�����㕔�Ɏ�������(����)��m�@�A���̓��������B
�����h
�����h
17���I�㔼�Ƀ��V�A������ɂ����čs��ꂽ�T����v(�j�R���̉��v)�̎��������ۂ������̓T��ɌŎ����Đ�����������������h�̑��́B
�ËV���h�A�����k�Ƃ��Ă��B
�����h�ɂ͂���Ɋe�n���ɗl�X�ȑ召�̏@�h(�Z�N�g))������A�ڐg�h�A�����h�A���S�h�Ȃǂ́A���̑�Z�N�g�ɂ�����B
���A�h�X�g�G�t�X�L�[�͕����h�ɊS�������Ă���A�h�X�g�G�t�X�L�[�̒����ȍ~�̏����ɂ́A���̕����h(�ڐg�h�A�����h)�̐M�k�Ǝv����o��l���������Γo�ꂵ�Ă���B
�ڐg�h
�����k�Ƃ͕ʂɁC17���I�O���Ɍ��ꂽ���h(�@�h)�B�����ڂőł�����M���I�ɗx�����肵�Ĝ������ɂЂ������̂ł����Ăꂽ�B�����h�̒��̈�@�h�Ƃ��đ������Ă���B
���A�w�߂Ɣ��x�̃��U���F�[�^�Ȃǂ��ڐg�h�̐M�҂��Ƃ���Ă���B
�����h
18���I�ɕڐg�h�̐��I����ᔻ���āA���I�s�ׂ�r���Ă������߂ɁA�M�k���A�X����[�̐؏����s�����Ƃ��n�߂��@�h�B
���A�w���s�x�̃��S�[�W���A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̃X�����W���R�t�Ȃǂ������h�̐M�҂��Ƃ���Ă���B
�Q�l�ƂȂ�{
�ȉ��A���V�A����(��������A�M���V������)�A�e���h�Ɋւ��ď����Ă��ĎQ�l�ɂȂ�{�������܂����B
���c�������߂̂Ԃ�B
���c���ݎs�̂���Ă���Ԃ�B
���c�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ����郍�V�A�����E���h�ɂ��ĐG��Ă�����́B
�E�w�M���V�������x��
(�u�k�Њw�p���ɁB�����ۍs���B1980�N���ŁB)����
�E�w�_�ƈ����\�M���V�������̐l�Ԋρx
(�p��I���B�����ۍs���B1994�N���ŁB)����
�E�w�M���V�A��������x
(������Y���B������1977�N���ŁB)
�E�w�M���V����������x
(�����x�j���B1978�N���B���o�ŎЂ́A�������B)
�E�w���V�A�����̐�N�x��
(NHK�u�b�N�X�B�A�����v���B1993�N���ŁB)��
�E�w���V�A������̗��j�x
(N�]�[���m�[�t���A�{�{����B1991�N���{����c�o�ŋǏ��ŁB)
�E�w���V�A����j�x
(N�]M�]�[���m�[�t���A�{�{������B1990�N�P���Џ��ŁB)
�E�w����������x
(O�]�N���}�����A�▴�c�C��E���Ύ��N��B������1977�N���B)
�E�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃM���V�������v
(�Ö쐴�l�M�B)��
�k�w���|�ǖ{�h�X�g�G�[�t�X�L�[(�T)�x(�͏o���[�V��1976�N���ŁB)�ɏ����B�l
�E�w�h�X�g�G�t�X�L�[�\���_�_�̍����x��
(�▴�c�K�q���B�ߑ㕶�|��1988�N���ŁB)�̒���
�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃ��V���̐����\�w��Ƃ̓��L�x�𒆐S�Ɂv(p255�`p274)��
�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƕ����h�v(p295�`p325)��
�E�w���V�A��ǂ݉����x
(�u�k�Ќ���V���B�A�����v���B1995�N���ŁB)���̒���
�u�_�̃��V�A�Ɩ��_�_�v(p79�`107)�B��
�E�w�\�r�G�g�ƃ��V�A�x
(�u�k�Ќ���V���B�X�{�ǒj���B1989�N���ŁB)���̒���
�u��݂�����_�X�\���V�A�����Ƌ��Y��`�v(p115�`136)�B��
�E�w�L���X�g����m�鎖�T�x
(�����������B�������o��1996�N���ŁB)���̒���
�u��������v(p162�`p173)�B
�E�w�L���X�g���̗��j�x
(�u�k�Њw�p���ɁB���c�_��璘�B1995�N���ŁB)���̒���
�u��������̎����v(P228�`P237)�B��
�E�w�L���X�g�������̏펯�x
(�u�k�Ќ���V���B���}���[���[�Y���B1994�N���ŁB)���̒���
�u����������v(p146�`p147)�B
�E�w�h�X�g�G�t�X�L�[�x
(��g�V���B�]��쒘�B1984�N���ŁB�u�]�`�I�v�V���[�Y�̓����Ł�����B)�̒���
�u���V�A�̓y��A���V�A�̐_�X�v(p87�`p168)�B����
�E�w������u�߂Ɣ��v�x
(�V���I���B�]��쒘�B�V����1986�N���ŁB)���̒���
p38�`p39�Ap190�`p192�B��
�E�w������u���s�v�x
(�V���I���B�]��쒘�B�V����1994�N���ŁB)���̒���
�u�u�����̃i�X�^�[�V���v�v(p101�`p119)�B��
�E�w�ǂ�ŗ����鐢�E�̗��j�ƕ����\���V�A�x
(�����ďC�B1994�N�V���Џ��ŁB)���̒���
p64�`p70�B
�T�C�g
���́A���V�A�����ɂ���
������Ă���T�C�g�ł��B
�E���{������HP
�P�O
�����̒P��
( �d�� )
�E�t���g
�@�c�@400�O�����B
���|���h�A��(����)
�p���A���َq�A
����݂Ȃǂ̏d
���ɗp����B�@
�E�v�[�h
�@�c�@14.38�L���O����
�l�̑̏d�Ȃ�
�ɗp����B
( ���� )
�E���F���W���[�N
�c�@��4.5�Z���`
�E�A�[���V��
�@�c�@��70�Z���`�@
�E�T�[�W�F��
�@�c�@2.1���[�g��
�߂������Ԋu��
�����̂Ɏg���B
�E�I��
(���A���F���X�g)
�@�c�@1.067�L�����[�g���@
���̂�̋�����
�����̂Ɏg���B
�P�P
�a�E��l
[����]
�E�������[�W���C
(���s��)
�E���q�|�R���f���[
�E់��a��
�E��
�P�Q
(���̑�)
[����]
�G��
�E�z���o�C����
�u�C�G�X�E�L���X�g�̎r�v
�E�N���[�h�]��������
�u�A�L�X�ƃK���e���v
���@�@�@���@�@�@��
�n���X�E�z���o�C����
�u�C�G�X�E�L���X�g�̎r�v
�ƃh�X�g�G�t�X�L�[
�n���X�E�z���o�C����
�u��̒��̎�����L���X�g�v
(�X�C�X�̃o�[�[�������ّ��B
1521�N��B)
������
���̊G���o�[�[�������قŖڂɂ������̃h�X�g�G�t�X�L�[�̐q��Ȃ炴�铮�h�E�S�Ԃ�́A
�A���i�E�h�X�g�G�t�X�J�����w�A���i�̓��L�x(�؉��L�[��B�͏o���[�V��1979�N���B)
�̒��ɋL����Ă���(1867�N8��24���̓��L�Bp345�B)�B
�����̒��ł́A
�w���s�x�̒��́A
��2�҂�4(�V�����ɂ̏㊪��p405�`p407)�A��3�҂�6(�V�����ɂ̉�����p160�`p163)
�ŁA�G����Ă���B
�w���s�x�̒��̂��̉ӏ��̉��߂Ƃ��ẮA
�������V��w�h�X�g�G�t�X�L�[�E���Ǝ��̊��o�x(��g���X1984�N���ŁB�s�̒��B)�̒���
�u�V�u��̒��̎�����L���X�g�v�Ɍ������́\���̔Đ_�_�Ǝ��̎��R�Ȋw�v
���Q�l�ɂȂ�܂��B
�n���X�E�z���o�C��
�h�C�c�̉�ƁB1497�`1543�B
�f���[���[�ƕ��ԃh�C�c���l�T���X�̑�ƁB�X�C�X�̃o�[�[���̂ق��A�p�E���E�C�^���A�Ŋ����B���ɏё���ɂ�����A�ё���ƂƂ��Ă͎j��ő�̉�Ƃ̈�l�Ƃ��Đ�������B����Z���L���ȉ�ƂƂ��Ēm���A���Ɠ����̂��߁A���n���X(�n���X�E�z���o�C���E�W���j�A)�ƌĂ��B
�ق��̑�\��Ƃ��āA
���u�}�C���[�s���̃}�h���i�v
�u�w�����[�������v�u���b�e���_���̃G���X���X�v�u�g�[�}�X�E���A�Ƃ��̉Ƒ��v�ȂǁB
�u�}�C���[�s���̃}�h���i�v���A�w���s�x�Ō��y����Ă���(�㊪��p140)�B
�N���[�h�]��������
�u�A�L�X�ƃK���e���v
�ƃh�X�g�G�t�X�L�[
�N���[�h�]��������
�u�A�L�X�ƃK���e���v
(�h�C�c�̃h���X�f�����p�ّ�)
������
�w�����N�x�̑�3����7�͂�2(�V�����E���w�ł́Ap565)
�ŁA���F���V�[���t�́A�h���X�f�����p�قŌ������̊G�̐��E���u��������v�ƌĂсA�̂��Ɏ����̖��̒��Ɍ��ꂽ���̂Ƃ��āA��z���ďq�ׂĂ���B
�w�����N�x�̒��̂��̉ӏ��̉��߂Ƃ��ẮA
�������V��w�h�X�g�G�t�X�L�[�E���Ǝ��̊��o�x(��g���X1984�N���ŁB�s�̒��B)�̒���
�u�S�u��������v�̖��\�y���̐����x����C���v
���Q�l�ɂȂ�܂��B
���́u��������v�̃C���[�W�́A�w����x�w�������Ȑl�Ԃ̖��x�Ȃǂł��o�ꂵ�Ă���B
���A���������ɂ́A�N�A�L�X�Ɣނ�����������K���e���̈��������p���`����A��ʉE�̒f�R�̏�ɂ́A�K���e���ɗ���������ڂ̋��l�L���N���[�|�X�������Ă��Ă���p��������B
�N���[�h�E������
�t�����X�̕��i��ƁB1600�`1682�B�v�b�T���ƂƂ��Ƀt�����X�ÓT��`�G����\�����ƁB
���j��_�b�Ɏ�ނ����s��ȍ\�}�̍�i�������A���Ƒ�C�ɒ��ڂ������i���`�����B�u�A�L�X�ƃK���e���v���A�I���B�f�B�E�X(���[�}�̎��l)�́w�ϐg杁x���瓾�Ă���B�ق��ɁA��\��Ƃ��āA�u�N���I�p�g���̏㗤�v�u�V�o�̏����̏�D�v�u�����̍`�v�ȂǁB
|
![]()