ドストエフスキーの小説 (2)
『罪と罰』について
(更新:25/12/26)
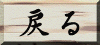
これから読む人は、以下、ネタ
ばれの箇所(▲〜▲の箇所)に注意!
『罪と罰』
(原題:
Преступление и
наказание)
〔事項〕
概要、登場人物
(更新:25/12/26)
成立・連載までの経過
この小説のテーマ
(更新:25/12/26)
概要、登場人物
(更新:25/12/26)
長編小説。舞台はペテルブルク。元大学生の青年ラスコーリニコフは、自己の閉塞(へいそく)の打開を求め、独自の犯罪哲学のもと、▲金貸し老婆アリョーナの殺害を強行してしまうが▲、その犯行後、彼は世間との断絶感に苦しみ、彼に目を付けた切れ者の予審判事ポルフィーリイの追及をかわし、謎の人物スヴィドリガイロフ(妻マルファを亡くしたのちラスコーリニコフの美貌の妹ドゥーニャに言い寄る初老の高等遊民)の交渉を受けていく中、▲聖なる娘ソーニャ(飲んだくれの退職官吏マルメラードフの娘。一家の生計のため、やむなく娼婦の身になっている)と出会い、彼女の感化とすすめで、ついに自首し、彼の更生を暗示させる流刑地シベリアでのソーニャ同伴の流刑生活▲までを描く犯罪小説・推理小説・恋愛小説・社会小説。
他に、世話好きの友人ラズミーヒン、ドゥーニャに求婚する俗物弁護士ルージン、進歩主義者の青年レベジャトニコフ(ルージンの知り合い)、青年医師ゾシーモフ(ラズミーヒンの友人)、▲老婆殺害直後に巻き添えをくってラスコーリニコフに殺害されてしまう中年女リザヴェータ▲、肺病やみで気位の高いカチェリーナ(マルメラードフの後妻)、その子供たち(ポーレチカ、リードチカ、コーリャ)、田舎からドゥーニャとともにラスコーリニコフのもとへ尋ねてくるプリヘーリヤ(ラスコーリニコフの母)、警察署の面々(署長ニコージム・フォミッチ、火薬中尉のあだ名を持つ副署長イリヤ・ペトローヴィチ、書記ザミョートフ)、下宿屋の話し好きの若女中ナスターシャ、犯人の容疑を受けたペンキ屋ミコールカなども配されている。
成立・連載までの経過
65年6月に月刊雑誌「祖国雑誌」に『酔っぱらい』(『罪と罰』の原型)の掲載を申し込むが掲載を断られる。
同年7月〜10月の借金取りから逃れるために発った三度目の外遊の間に新たに小説の構想を練り、賭博にふけって一文なしになった宿で『罪と罰』と題して起稿。9月に友人を通して月刊雑誌「ロシア報知」に売り込みを依頼。
同年11月に第一稿を消却し三人称形式で新たに書き直した。最終の形をとった『罪と罰』は、66年1月から12月まで(45歳時)、「ロシア報知」に連載された。
なお、同年10月に婦人速記者アンナの助けを借りて中編『賭博者』を完成させたのちも、引き続いてこの小説の末部(第六部の一部及び「エピローグ」)もアンナとの口述筆記で完成させている。
この小説の連載は、ロシアの読書界に大きな反響をもたらし、ドストエフスキーは作家としての地位をより堅固なものにした。
この小説のテーマ
(更新:25/12/26)
(1)
・踏み越え(プレストプレーニエ)というテーマ。選ばれた人間(非凡人)、または、理性や合理主義にしたがって大義名分を掲げた人たちには、人を殺すなど、世間の法を平気で乗り越えていく権利があるのかどうかという問いかけ。
または、
・主人公の状況(学業や仕事もしないで引きこもって考え事ばかりしている)を踏まえて、自己の閉塞状況の打開のための乗り越えの行為ということ。
※、ただ、そのために行う行為がなぜ老婆殺しになるのかという疑問は残るが、たとえば、
作者はこの小説でロシア人とユダヤ人の葛藤を描こうとしたのであり、主人公ラスコーリニコフはまちがいなくロシア人であり、高利貸の老婆はユダヤ人を象徴している
という宇野正美氏の見方あり。
また、作中では、ソーニャのことにもこの「乗り越え」は適用されていることには注意したい。
※、清水正氏による「神の時空に一挙に飛び超えることを企(はか)った」という宗教的な内容を含む見方もあり。
(2)
驕(おご)りによる殺人(=「罪」)、それを犯して孤絶と罪意識にさいなまれる犯罪後の人間の状況や心理(=「罰」)
という犯罪心理を克明に描写すること、
そして、
・理性と合理主義に基づく無神論の驕りからキリスト教的謙抑へ、
・思弁から「生活(ジーズニ)」・生ける生・復活・新生へ
というテーマ(彼のその後の悔悛・更生)
を打ち出すこと。
ラスコーリニコフはシベリア送りとなった終盤に至っても自分の犯した行為の罪性を自覚し悔悛していくことできないが、作者は、
・聖女ソーニャとの出会い
・彼の苦悩を知り彼に寄り添って生きようとする彼女への罪の告白、聖書の「ラザロの復活」を読んで聞かせた彼女の指図による自首と懺悔、
・流罪地でやがて彼女を愛するようになった相愛と彼女の様子を眺めて何かが心を貫いた体験
等を通して、彼の将来の更生・救済を示唆している。予審判事ポルフィーリイもその追究の中でまだ若い彼に更生を勧めている。
(3)
苦境の中でのマルメラードフの思いのたけの描写と、彼のような自制・克己がうまくできない人間の救済・更正のこと(行き詰まっているマルメラードフの語り・絶唱を通して、彼のようなダメ親爺ぶりと飲んだくれの悪癖を克服できずに低迷して苦しむ人間の神への信仰とその救済・更生といったことを作者は問いかけている。)
その他の特筆事項
・当時の真夏のペテルブルクの社会や風俗などをいろいろと描写している小説としても貴重。
・江川卓氏が『謎とき『罪と罰』』で指摘した通り、この小説の創作においては、作者は、細部に様々な凝った工夫や仕掛けを施している。
末部は妻となったアンナ夫人との共同の口述筆記となったが、末部までの創作は作者個人の工房で専念されたということがその背景として考えられる。
・当時起こったいくつかの同様の殺害事件を、取材し、モデルにしている。
・ラスコーリニコフとソーニャは、前作『地下室の手記』の主人公とリーザの発展形となっている。
スヴィドリガイロフは『虐げられた人びと』のワルコフスキー公爵を継承している。
・肺病やみで気位の高いカチェリーナは作者の最初の妻をモデルにしている。
作者の青年期の逮捕と尋問の体験は、主人公と予審判事ポルフィーリイの対決に生かされている。
・主要登場人物の設定などにおいて、聖書のヨハネ伝の中のラザロの復活の話における人物関係、プーシキンの『スペードの女王』、バルザックの 『ゴリオ爺さん』(スピドリガイロフはヴォートランを踏まえている?)を下地にしているとの報告あり。
『罪と罰』を論じた本や論
・内容を論じたもの
(
1
2
3
4
)
・論
(
1
2
3
4
)
・主要登場人物を論じたもの
(
1
)
《邦訳・一覧》
★はおすすめのぶん。
米川正夫訳
岩波文庫、
角川文庫、
河出書房版全集(巻7巻8)
小沼文彦訳
筑摩版全集(巻7)
江川卓訳★
岩波文庫、
旺文社文庫
工藤精一郎訳
新潮文庫、
新潮社世界文学
新潮社版全集
北垣信行訳
講談社文庫、
講談社世界文学
全集(巻44)
池田健太郎訳
中央公論社文庫、
中央公論社の
文学(巻16)
小泉猛訳
集英社のギャラリー「世
界の文学」(巻14)
中村白葉訳
岩波文庫、
新潮文庫
亀山郁夫訳
光文社古典新訳文庫
内田魯庵訳
「文学雑誌」に前編
を連載・発行(明治25年)。
明治文学全集巻29、
内田魯庵全集第12巻
< 映画化・漫画化されたもの >
・『罪と罰』( 1 2
)
・ドラマ『罪と罰』(
1
)
・マンガ『罪と罰』(
1
)
|
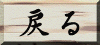
![]()
![]()